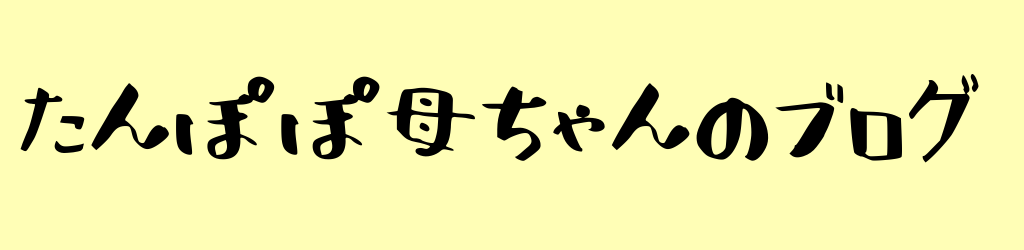スポンサーリンク
こんにちは、重度障害児の母、たんぽぽ母ちゃんです。
お子さんが薬を飲まなければならなくなったとき、
甘いシロップもダメ、粉薬なんてもっと無理!
そんなお子さんは多いと思います。
今回は、
子どもの粉薬の飲ませ方〜最も効果的な方法は〜
子どもに粉薬を飲ませる方法は、結論から言うと、
理由は、薬は頑張って飲むもの、甘い食べ物は楽しんで食べるもの、と分けたほうが、お子さんが混乱しないからです。
下手に甘いものと混ぜると、甘いもの自体が嫌いになってしまうこともあります。
ただ、少量の場合や、
以下に、他の食品を使う場合のおすすめの飲ませ方を紹介しておきます。
◯他の食品と一緒に飲む方法
うちでも、他の食品でごまかす方法は、
- ゼリーに挟む
- チョコアイスに挟む
- バナナに挟む
•ゼリーに挟む
 ゼリーに挟む場合、
ゼリーに挟む場合、苦い薬だと、ゼリーの水分に少し溶けただけで、
もしやる場合は、「おくすりのめたね」
チョコ味だと、苦味がいくらか気にならない感じがします。
まずスプーンに少量のゼリーを出し、その上に粉薬を入れます。
さらにその上にゼリーを乗せれば、上手に挟むことが出来ます。
•チョコアイスに挟む
 チョコアイスは、食品を利用する中では、一番おすすめの食品です。
チョコアイスは、食品を利用する中では、一番おすすめの食品です。チョコアイスで薬を挟む方法は、冷たさと味で、苦味を感じにくくなります。
ちなみにうちの2番目の子は、チョコに目がなかったので、
難点は、アイスが溶けやすいので、
また、好きなアイスを味わおうとするため、
下の子は、2歳頃にためして「苦い〜」と言っていましたが、
•バナナで挟む
 薄くスライスしたバナナに、薬を挟む方法です。
薄くスライスしたバナナに、薬を挟む方法です。薬は1番挟みやすいですが、噛んでしまうとジャリッとした食感があります。
3歳くらいになり、
バナナを潰したものをゼリーのように使えば、
凍らせたバナナに、牛乳、バニラエッセンス、砂糖を加えてミキサーすれば、バナナシェイクのようになりますよ。
しかし、障害のあるうちの子はこれもダメ。
しまいにはバナナの匂いも味も、
(5年ほどバナナ断ちをして、
うちの子の場合は、一緒に食べさせた食品は、薬が混ざっていない時にも、もれなく警戒するようになり、嫌いになってしまったのです。
◯粉薬をそのまま飲む方法
粉薬をそのまま飲むにも、少しコツがあります。
以下の2パターンを試してみて下さい。
- 薬に少量の水を加えて、ねって団子状にし、
お子さんのほっぺの奥に擦り付け、すぐに水で流し込む方法 - 10ccほどの水に溶いて、シリンジやスポイトで、
なるべく舌に当たらないように流し込む方法
①薬に少量の水を加えて、ねって団子状にし、
まず、粉薬に本当に少量の水を加えて、
それをお子さんの口の中、ほっぺの内側にこすりつけます。
なるべくほっぺの奥側、喉に近い場所にすると、
団子を付けたら、素早くシリンジやスポイト、
デメリットとしては、水分の調整が難しいことと、
うちの子の場合、この方法も口に手を入れられることが嫌で、暴れてしまいだめでした。
格闘しているうちに、薬の団子も落としてしまうんですよね。
おとなしい子なら良いのかもしれません。
②10ccほどの水に溶いて、シリンジやスポイトで、
食品に混ぜるのもダメ、団子もダメとなり、最終的に、うちはこの方法で飲ませていました。
まず薬の量に合わせ、ちょうどよく溶けるくらいの水で、
(一般的には薬杯を使うことが多いとおもいます。)
それを、スポイトやシリンジで吸い上げ、飲ませます。
飲ませる時は、舌の上ではなく、ほっぺの内側の、
注意点としては、
子どもが一回で飲み込める量は5ccくらいまでなので、
おまけ【我が家の薬の溶かし方】
補足として、うちの場合の薬の溶かし方を紹介しておきます。
服薬の量が多い、
うちでは、薬杯を使わず、シリンジだけを使用します。
①まず、シリンジで水を吸い上げ、押し出します。(
※先端にラップなどをしておくと、こぼれず便利です。
②シリンジが真っ直ぐ立つように置きます。
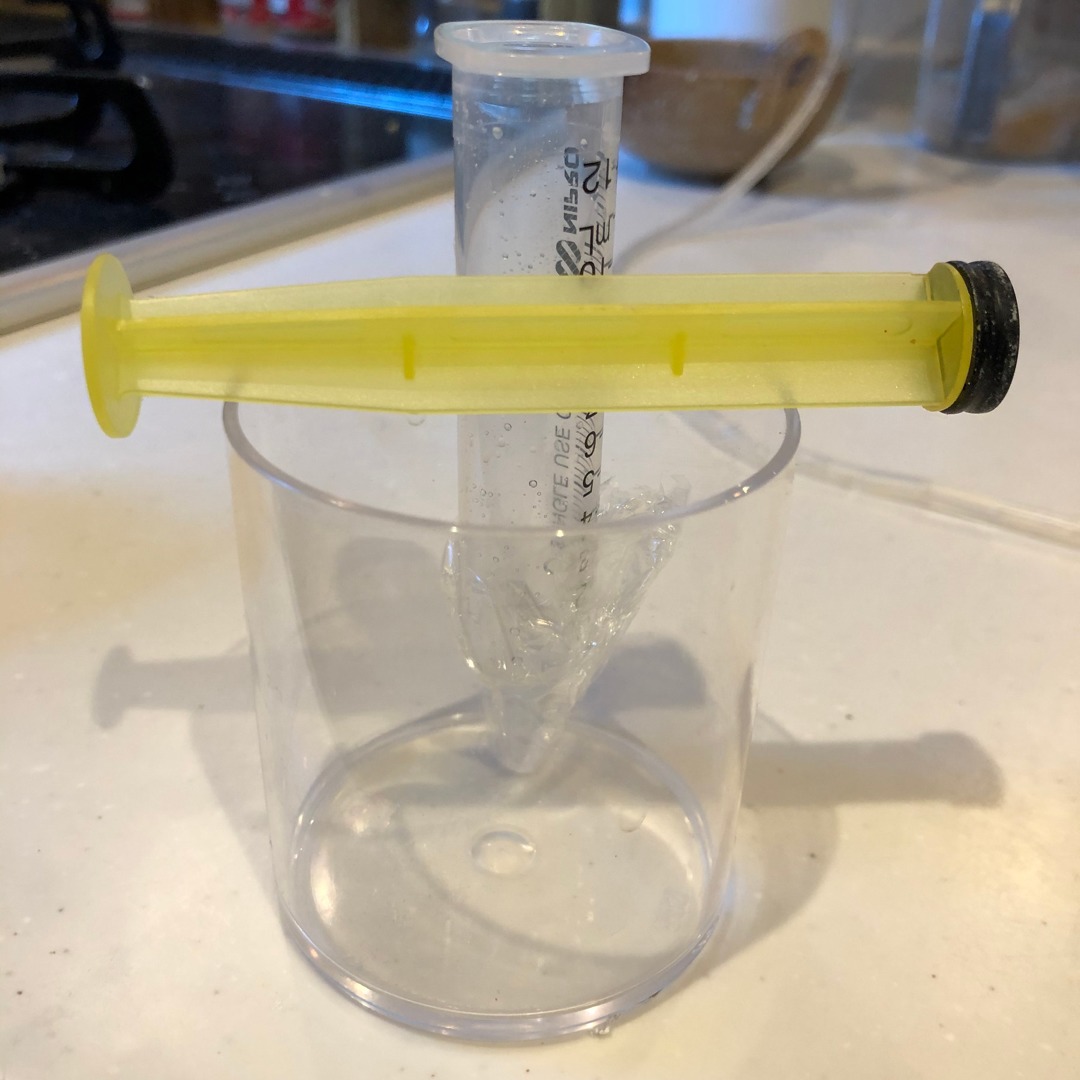
③ここに、薬を直接入れていきます。
※錠剤がある場合は先に錠剤を入れたほうが、
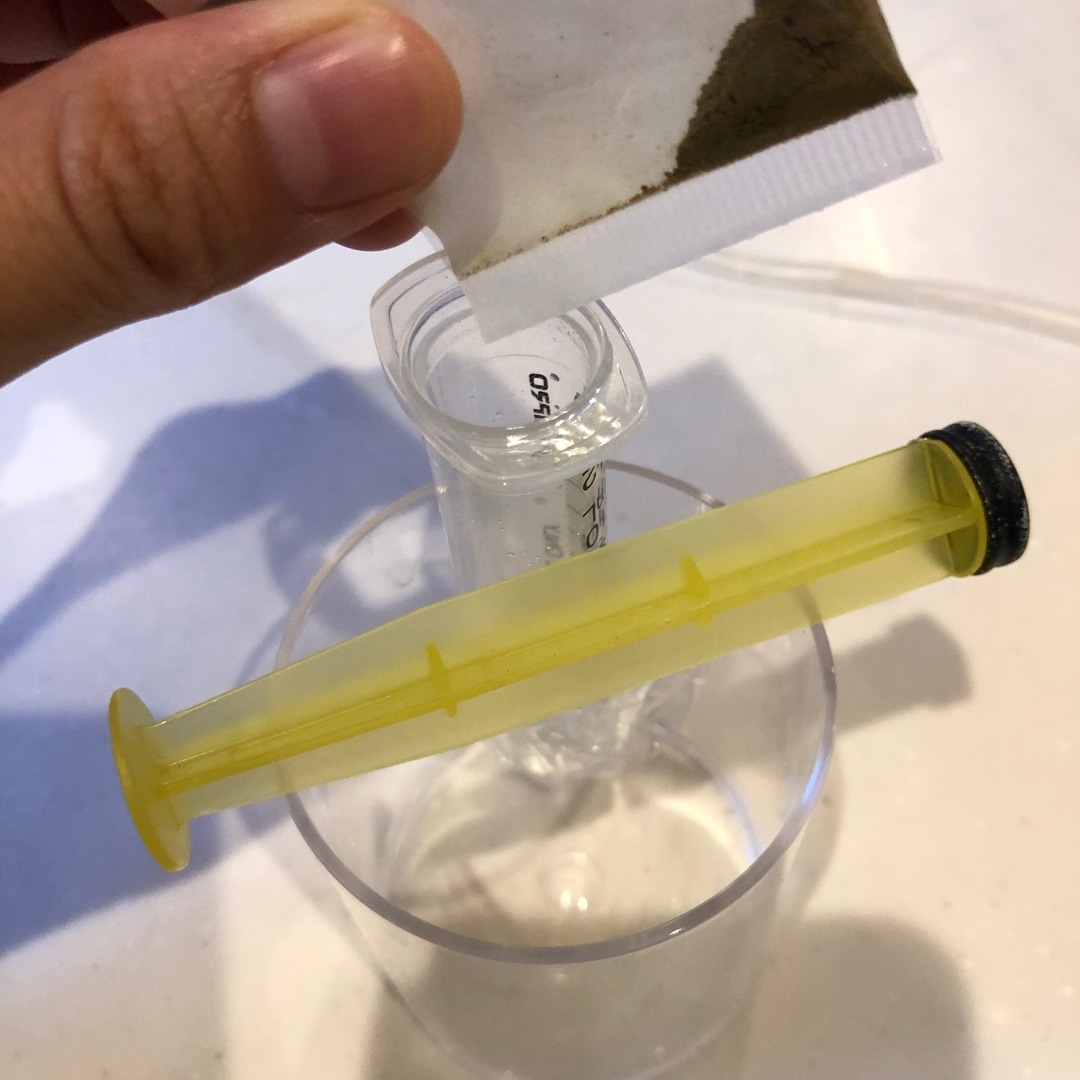
④シリンジに軽く蓋をし、先端を指で抑えながら(
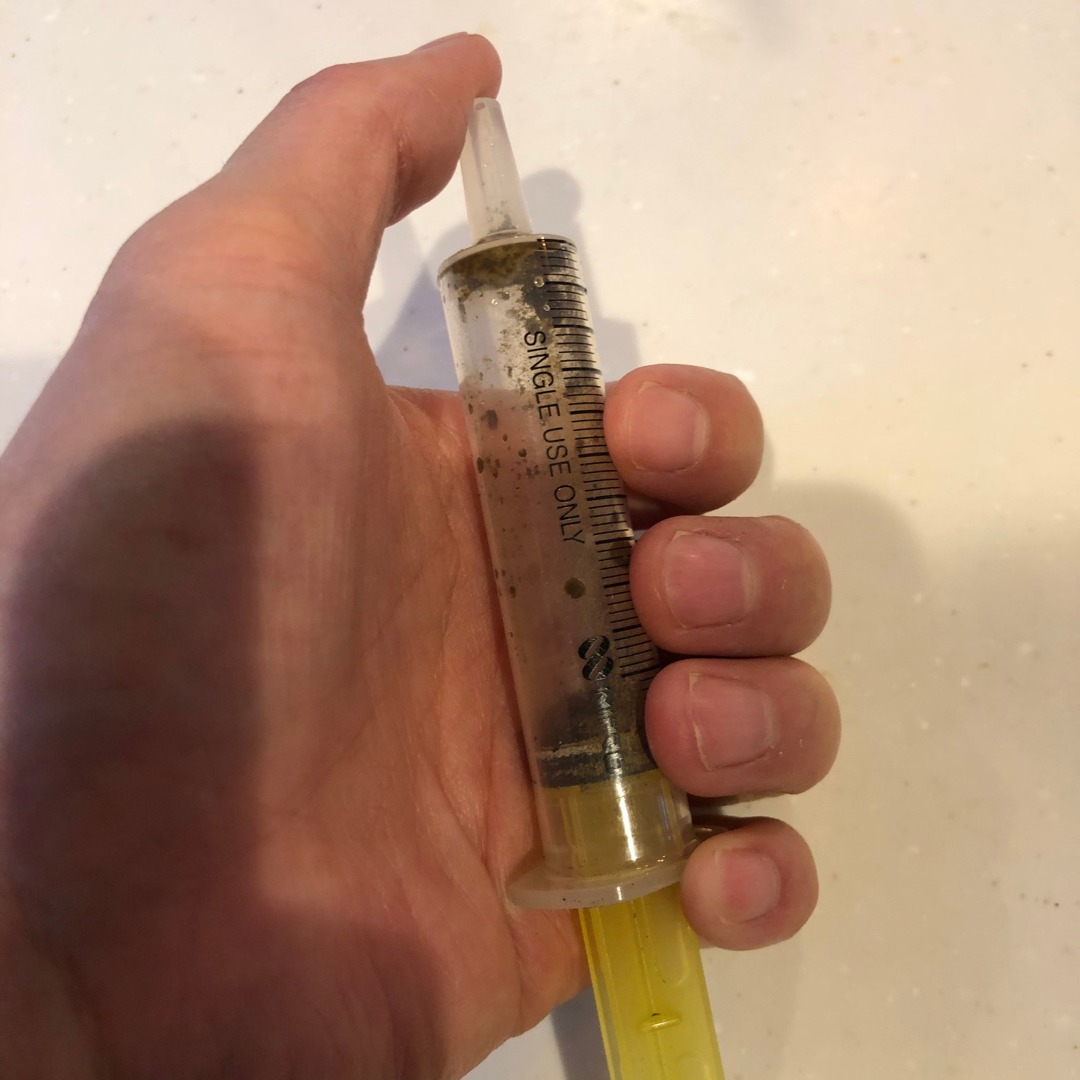
⑤水を吸い上げ、薬を良く溶かします。
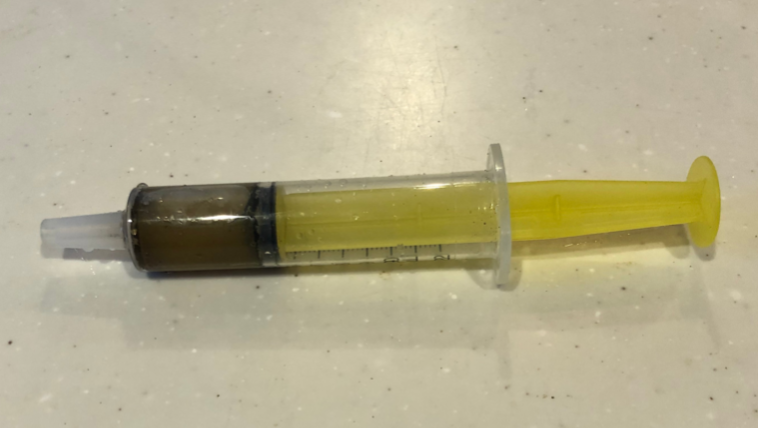
薬を飲ませる時は、
もしも泣いている場合は、呼吸に合わせて薬を飲ませます。
うちの子の場合、泣き声の終わり頃、
泣き声が終わるまで待ってしまうと、
まとめ
他の食材を使った場合、
うちの場合は甘いもの全般がしばらく(何年も)
食事(楽しみ)と薬(頑張ること)は分けるほうが、
薬を頑張った後のご褒美として、薬を飲んだあとに甘いものを食べさせ、口直しをする、というのが良いのかなと思います。
うちの子どもは持病でてんかんがあり、それを抑えるために、
また成長に伴って服薬の量も増えていき、薬を飲ませることが、
てんかん薬は少量でも効果が大きく変わってしまうため、
毎日毎日、試行錯誤しながら、どうにか薬を飲ませてきました。
2歳半で経鼻経管になってからは、
長男がだいぶ大変だったので、2人目3人目は楽勝!
お子さんによって、合う合わないもあると思いますので、
お子さんの服薬に苦労されている方がいましたら、
障害児育児は上手に福祉サービスを利用していくことで楽になります。
散髪や入浴も悩みの種ですが、我が家ではほとんどを福祉サービスに頼っていますよ。
また、障害児育児が辛いと感じる方は、こちらの記事も参考にしてみてくださいね。
スポンサーリンク